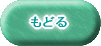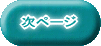|
 |
| �i���ߑ��E�w��Maianthemum dilatatum�j�̓X�Y�������ȃ}�C�d���\�E���ɑ����鑽�N���B���[���V�A�k�����i���V�A�����A���{�A���N�����j�Ɩk�A�����J�k�����i�A�����J���O���J���t�H���j�A�B�k���A�I���S���B�A�A���X�J�B�A�A�����[�V���������Ȃǁj�ɕ��z���A���{�ł́A�k�C�������B�̎R�n�я㕔���爟���R�т̐j�t���тɑ����Q������[1]�B �k�A�����J���́A���ݕ��̉��щJ�тɑ����A�悭�V�g�J�g�E�q�т̎����ɌQ
������B
���t�w�i���^�[�w�j�̔��B�������ŁA���s�����ɐL�������ɐB����B�s�͍���10-20cm�قǗ����オ��A�r����2�����n�[�g�`�̗t������B�Ԋ���5-7���B��[����s��L���A���F�̏��Z�ىԂ�ԏ��ɂ���B
|
�s�͑����~���`�Œ������A����30-60cm�ɂȂ�B�t��5-10�����s�Ɍݐ����A�t�g�͑ȉ~�`�`�����ȉ~�`�ŁA����7-15cm�A��2-6cm�B��[�͐��A���͔g��ɏk��A3-5�̗t�����ڗ��B�t�̊�͏��ɂȂ��Čs������B
�Ԋ���5-7���ŁA�W�g���F�̉Ԃ���ɑ�������B䚂͉Ԃ����������B�ӕЂ͒���5mm�A���ԕق��ӕЂ��Z���A�O�ق͂�������A�����я�L���`�Ő�[��3��B
�a���̗R���́A�����̃e�K�^�`�h���̔���������s�̌`�������Łu��`�v�ł���̂ɑ��A�{��̍��͏���ɂȂ炸�A�L�т邽�߁u�����v�Ƃ����B
�����A�J���`���c�J�����A���N�����A���{�ɕ��z����B�R�n�����щ��̎������ꏊ�Ɏ�������B
���{�ł͖k�C���A�{�B�����Ȗk�A�l���A��B�ɕ��z����B
|
 |
 |
| �U���s�͗��`�B�U���s�̒����ɂ��z�~���̗t�͋������~�`�Ŋv���A����15-35cm�A��3-5cm�Ő�[�͐��B�ӂ�1�t�����B�t�̊�͏��ɂȂ��Čs������B
�Ԍs�͒������A������30-50cm�ɂȂ�B�Ԋ���5-6���ŁA�W�����F�̉Ԃ�ԏ���10-20�Ԃ��������ɂ���B�ӕЂ����ԕق͐����j�`�Œ���3-3.5cm�A��4-5mm�A�O�ق͒���3cm�ōg���F�ɂȂ�B
���{�ł͓�瓇�A�k�C���A�{�B�A�l���A��B�ɕ��z���A�R�n�̗я��Ɏ�������B�A�W�A�ł͊����암�A���N�암�A�����i�{�y����ё�p�j�A�q�}�����ɕ��z����B
�a���̗R���́A�ԏ��̗l�q����Ŏw�����������w�������єz�Ɍ����Ă����́B
|
�V���l�A�I�C�i�������A�w���FGlaucidium palmatum�j�́A�L���|�E�Q�ȁi�V���l�A�I�C�ȂƂ��ĕ����邱�Ƃ������j�V���l�A�I�C���̑��N���̈��B�[�R�̐A���B���{�ŗL���1��1��ł���B
�k�C������{�B���k���̓��{�C���ɂ����Ă̎R�n�тƈ����R�т̂�⎼��C�̂���Ƃ���ɕ��z���Ă���[2]�B������20-30 cm�B�Ԋ���5-7�����B�ԕق͂Ȃ��A7 cm�قǂ̒W�����F�̑������ӕЂ�4������A��ϔ������p�����Ă���B
�a���́A���������R�ɑ����A�Ԃ��^�`�A�I�C�Ɏ��邱�Ƃ���V���l�A�I�C�i�������j�Ɩ��Â���ꂽ�B�ʖ��Łu�R���u�i��܂ӂ����j�v�A�u�t���u�i�͂�ӂ悤�j�v�Ƃ������B
|
 |
 |
| ���n�Ɏ��������蒼��̗t�Ԓ������珃���̕���䚁i�Ԃ���ق��j�ƌĂ��䚂��J���B���ꂪ�ԂɌ����邪����䚂��t�̕ό`�������̂ł���B����䚂̒����ɂ���~����̕����������ȉԂ������W�܂����ԏ��i������j�ł���B�J�Ԏ�������n�ł�4������5���A���n�ł͗Z����5������7���ɂ����āB�t�͉Ԃ̌�ɏo��B���o��ɏo�ė����オ��A����80 cm�A��30 cm�ɒB����B
�a���́u�o�V���E�v�́A�m�ԕz�̍ޗ��ɗ��p����Ă���C�g�o�V���E�̗t�Ɏ��Ă��邱�ƂɗR������B
�V�x���A�����A�T�n�����A�瓇�A�J���`���b�J�����Ɠ��{�̖k�C���ƒ����n���Ȗk�̖{�B�̓��{�C���ɕ��z����B
����̕��Ɍ��{���s�̉��ۍ⓻�ɂ��u�����z���Ă���B�R�n�т��爟���R�т̎�����щ��̎��n�ɕ��z����B�w���̎������́u�J���`���c�J�����v�ɗR������B��W�{�́A�J���`���b�J�����̂��́B
|
|
 |
 |
| �����Z�����s����A����20-50cm�̌s����{�L�сA���̐�[��3���̗t�������B�t�͗t�����������A�s���璼�ڐ�����B�t�̌`��͊ۂ݂�тт��Ђ��`�ŁA���a��10-20cm�B�Ԋ���4-6���B3���̗t�̒��S����Z���ԕ����L�сA�����ȉԂ�����B�Ԃ͉ԕق�������3���̗ΐF�܂��͔Z���F�̂����Ђ������A�������ɍ炭�B
���{�ł́A�k�C���A�{�B�A�l���A��B�ɕ��z���A��n��R�т̂�⎼�����ꏊ�ɐ�����B���A�W�A�ł́A�T�n�����i�����j�A��瓇�ɕ��z����B
�����n�����ʎ��͐H�p�ƂȂ�B
���s�͒����ł͉�����ƌĂ�A�Â�����ݒ����Óf�܂Ȃǂ̖Ƃ���邪�A�T�|�j���Ȃǂ̗L�Ő������܂ޗL���A���ł���A�ߗʂɕ��p����A�q�f�A�����Ȃǂ̒��ŏǏ���N�����B
|
|
 |
 |
| ���o�t�͒����t���������đ������A�t�g�͐S�~�`����t�~�`�ŁA�����A���Ƃ�3-10cm�ɂȂ�A���ɂ͒Ⴂ���������B�s���������A�Ԍs�̍�����15-50cm�ɂȂ�B�s�͒���ŁA�s�t�͌s�̏㕔�ɂ��A���o�t�Ɏ��邪���^�ɂȂ�B
�Ԋ���5-7���B�s�̐�[����їt�����璷���ԕ���L���A�a2.5-3cm�̉��F���Ԃ�����B�ԕق͂Ȃ��A�ԕقɌ�����̂����ЂŁA�ӂ�5���A�Ƃ���6-7������B�Y�ǂ͑�������A���ǂ�4-12����B�ʎ��͑܉ʂƂȂ�A����1cm�ɂȂ�B���͔��F�Ńq�Q���ɂȂ�B�s���������A�����F�̉Ԃ����邱�Ƃ��痧���Ԃƌď̂����悤�ɂȂ����B�Ԍ��t�́u�K������K���v�B���̊w���ƂȂ��Ă���Caltha�̓��e����Łu���������̂��鉩�F���ԁv�Ƃ����Ӗ������B
|
|
 |
 |
| ������������{�S���̎R�т̔�r�I�Â��ꏊ�ɕ��z����B������30�`60cm�B�Ԋ���4�`6���B�s�̐�ɐ��{�i2�{�̏ꍇ�������j�̕��ԏ����o���A�����Ȕ����Ԃ�����B�Ԃɂ͉ԕق��ӂ��Ȃ��A3�̗Y���ׂ��ۂ��q�[������Ă���B�ԏ��͗��������邪�A�ʎ����ł���Ɖ��ɋȂ���B�č��i�ʎ��̐��n���j�ɕ����Ԃ�����B
�a���́A2�{�̉ԏ����A�\�y�u��l�Áv�̐Ì�O�Ƃ��̖S������p�ɂ��Ƃ������́B�q�g���V�Y�J�Ƒ𐬂��B�������A�ԏ��͓��Ƃ͌��炸�A3-4���������B
|
������10�`30cm�B�t��4��������ɕt��������A����
�͋���������B�Ԋ���4�`5���ŁA�s�̐��1�{�̕��ԏ����o ���A�u���V��̏����Ȕ����Ԃ�����B��{�Ő�����̂͋H�ŁA ���ʌQ������B���̗̂R���͂��̉Ԃ̉��������łĐÌ�O �ɂȂ��炦�����́B�߉���̃t�^���V�Y�J���ԕ��2�{�ȏ�o�� �̂ƑΔ䂳�����B �k�C���A�{�B�A�l���A��B�ɕ��z���A�R�n�̗ѓ��A�щ��Ɏ�
������B |
 |
 |
| �����Z�����s����A����20-40cm�̌s��1�{�L�сA���̐�[��3���̗t�������B�t�͗t�����������A�s���璼�ڐ�����B�t�̌`��͊ۂ݂�тт��Ђ��`�ŁA���a��10-20cm���x�B3�����t�̒��S����Z���ԕ����L�сA3���̊O�Ԕ�Ђ�3���̔������ُ�̓��Ԕ�ЁA6�{�̗Y�ǂ����Ԃ���B���Ԕ�Ђ͊O �Ԕ�Ђ�蒷���A�O�Ԕ�Ђ̐�[���Ƃ���B
|
�n���ɂ���،s�͗��`�Œ���10-15mm�ɂȂ�A�щ��F�̔���ɕ�܂��B���o�t��1�ŁA�`�͐��`�Œ���15-30cm�ɂ���A�����݂�����B�Ԍs�́A����15-25cm�ɂȂ�A2��䚗t�����B
�Ԋ���4-5���ŁA�Ԍs�̐��4-10�̉��F�̉Ԃ��U�`�������B�ׂ��ԕ��̒����͕s�K���ŁA1-5cm�B�Ԕ�Ђ�6���A���ȉ~�`�Œ���12-15mm�B�Y�ǂ�6����A�Ԕ�Ђ��Z���B�ʎ������ʂŁA3�ł����鋅�`��ɂȂ�A������7mm���O�ɂ���B
|
 |
 |
| �����̌��w�Ɏ����`�̉ԕق̏d�Ȃ肪�m�������T��g�ގp�Ɍ����邱�Ƃ��A���̗̂R���Ƃ����B�܂��A�Ԃ�B����t�̍��T����p�Ɍ����ĂāA�_���}�\�E�i�B�����j�Ƃ��ĂԁB
��сA����щ��юR�x�n�̎��n�ɐ��炵�A�J�Ԏ�����1�����{����3�����{�B�J�Ԃ���ۂɓ���ԏ��i�ɂ�����������j�Ŕ��M���N�����25���܂ŏ㏸����B���̂��ߎ��͂̕X���n�����A������������o�����ƂŁA���̎����ɂ͐��̏��Ȃ�������Ɛ����A�̊m�����グ�Ă���B�J�Ԍ�ɑ�^�̗t�𐬒�������B
|
�{�B�̒����Ȗk�A�k�C���ɕ��z���A��⎼��C�̂���ѓ��A�щ��Ɏ�������B
������1.5�`2.0m���炢�ɂȂ�A�Ԋ���7�`8���ŁA10�`20�����ΐF�̉Ԃ�����B���t�܂ŗ����͂ꂵ���A���������s���݂邱�Ƃ�����B
�Ԃ��������͈ꐶ���I���邪�A�����̘e�Ɏq��������Ă���B
�֓��n���Ȑ�����l���A��B�ɕ��z����E�o��������^�ŁA�Ԃ̐��������B
 |
 |
 |
| ���Ӎ��i�������j�Ƃ͐���̈��B���̐���̓P�}���\�E�Ȃ̐A���Ŋw��Corydalis turtschaninovii�܂��͂��̑������A���̉�s�̂��Ƃł���B �Y�n�͒����B
���{��Ǖ��Ɏ��^����Ă���A���z�A���ɍ�p�Ȃǂ�����A�����U�A���G�U�Ȃǂ̊������܂ɔz�������B�g�߂ȂƂ����ł́A�吳����ݒ���A���c�����ݒ���Ȃǂɂ��z�����������
|
������30�`50cm���炢�ɂȂ�B�t�͑ΐ����A���̌`�͗���3�p�`����L���`�ŏ㕔�̗t�͗��`�Ő悪�Ƃ���A���͑e��������ɂȂ�A��͐�S�`�ŗt��������[2]�B
�Ԋ���4�`6���ŁA�O�`�̔��F�܂��̓s���N�F�̉Ԃ��A������ԂɂȂ��Čs�̏㕔�̗t���ɐ��i�ɂ���B�Ԃ̂������A�}�����Ԃ����x��q�B�����p�Ɏ���B
�Ԃ̊�ɖ�������A�ώ@�����̍ޗ��Ƃ��Ȃ�B
|
 |
 |
| ���{�ł͖k�C�������B�ɂ����ĕ��z���R�тɐ��炷��B�V�m�j���i�������w�����ӌ�j�̎포���ł��� amurensis �́u�A���[���여��́v�Ƃ����Ӗ��B�Ԋ��͏��t�ł���A3-4cm�̉��F���Ԃ��炩����B�����͌s���L�т��A��ɕ�܂ꂽ�Z���s����ɉԂ����������A����Ɍs��t���L�сA�������̉Ԃ���������B���̉Ԃ͉ԕق��g���ē������Ԃ̒��S�ɏW�߁A���̔M�Œ���U�����Ă���B���ׁ̈A���z���ɉ����ĊJ�i������������ƊJ���A�����A��ƕ���j����B�t�ׂ͍����������B�Ăɂ���ƒn�㕔���͂��B�܂菉�t�ɉԂ��炩���A�Ă܂łɌ������������Ȃ��A���ꂩ��t�܂ł�n���ʼn߂����A�T�^�I�ȃX�v�����O�E�G�t�F�������ł���B
���̓S�{�E�̂悤�Ȃ܂������ő������̂𑽐������Ă���B
|
����20 - 30cm[6]�A��3 - 10cm�̗t�ŋ����j���j�N�L������A�n���Ƀ��b�L���E�Ɏ����،s�����A�t�͍����A�G���ʼn�������������ƂȂ�B���āA�Ԍs�̒��[�ɁA���F�܂��͒W���F�̏��Ԃ𑽐�����B��q�̂ق��ɂ��s���ł����B����B���瑬�x���x���d�킩����n�܂ł̐�����Ԃ�5�N����7�N�Ɣ��ɒ������Ƃ���A�ȎR�Ƃ���A�s��ɏo����Ă�����̂͏����ɂ�������炸���l�Ŏ�������X���ɂ���B
|